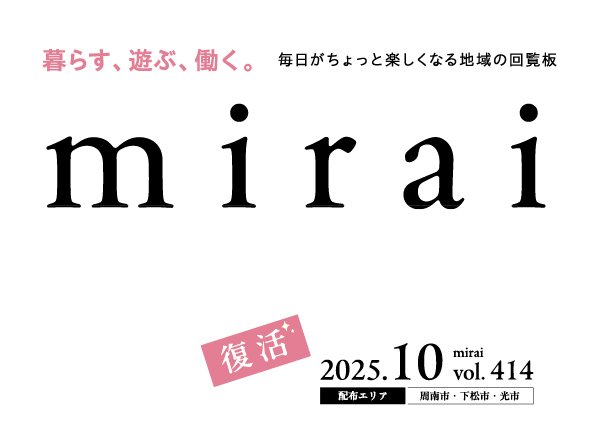コラム・エッセイ
7月豪雨から思うこと③ 〜「暑さ寒さを愚痴るだけの生き方」
おじさんも頑張る!~山の話あれこれ~ 吉安輝修長い梅雨がようやく明けたと思ったら、今度はいきなりの猛暑だ。昼過ぎに軒先にぶら下げてある温度計はなんと34度を指しているではないか。日陰でこれだから直射日光のあたるアスファルトの上は照り返しもあって40度以上にもなっているかもしれない。もはや人が普通に外で動ける環境ではないような気がする。
とはいうものの、先日までの長雨でしっかりと水分を含んだ大地に生える草木は、ふりそそぐ太陽の光で光合成も盛んでますます勢いが良い。長雨を言い訳に草刈りの手抜きをしていたツケが待ったなしで追いかけてくる。しばらくは風呂上りのビールだけを生きがいに大汗を覚悟だ。
«親不知を目指す»をのんきに書いていたが、日本中に甚大な被害をもたらした大雨のニュースを見聞きすれば、さすがに知らん顔ができずにしばし話題を変えていた。だが、ようやく全国的に梅雨も明けたようで一安心。次回からまたボチボチと役にも何にも立たない山歩きの話に戻ろうかと思っている。
が、被災地の片づけなどの復旧作業はコロナの影響で他県からのボランティア制限もあり、マンパワー不足だという。この猛暑の中、仮住まいをしながらの遅々として進まぬ重労働だ。被災された方の心中は察するに余る。
話題を戻すにあたり、今回の豪雨災害に関する報道からどうしても書き留めておきたいことがある。毎日新聞7月22日付け[雨脚が不穏 避難しろ]の見出しが目に留まった。
以下引用させてもらう。『〜球磨川が氾濫し、20人が亡くなった熊本県人吉市で、川を知り尽くした元ベテラン男性船頭の呼びかけにより市の指示を待たず住民が水没前に避難して人命被害を免れた地区があった。「降り方がおかしい」と感じた一橋さんは、地域の自主避難所となっている集会所に向かい、受け入れ準備を始めた。現役の船頭時代から増水時に川の水位を目視で測る習慣があったが、暗闇では見えず、川の水位観測データがリアルタイムで分かる国土交通省のサイトを確認した。
すると球磨川の水位は10分ごとに10センチ上昇し、3メートルを超えても同じペースで上がり続けていた。「これはただごとではない」。長年の経験からそう判断した一橋さんは、人吉市が全域に避難勧告を出す約1時間前の午前3時ごろ、呼び出した町内会の班長3人と手分けして、約50世帯70人が住む大柿地区全ての家を回り、住民をたたき起こした。―後略―』というものだ。
暗闇では見えない川の水位をインターネット上の水位観測データから入手して判断したというが、「川に生かされてきたが、球磨川に優しいイメージはない。自然を恐れ、危機意識を持たないといけない」と警告する一橋さんの体に染みついた自然への畏敬の念が根底にあったからに他ならない。科学万能で機械やAIとやらに頼り切る現代人がどこかに置き忘れてきた大事な感性だ。田舎暮らしとはいえ、いつしか暑さ寒さを愚痴るだけの生き方を反省。

須金でも錦川が増水し気をもむ日が続いた=水位をネット上で確認できればいいのだが…。