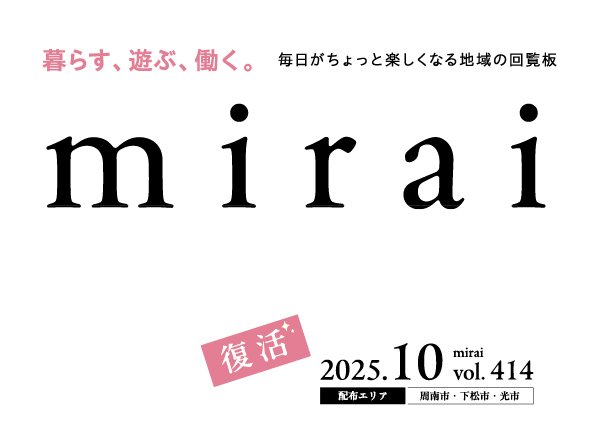コラム・エッセイ
親不知を目指す㉗「山なんかに行かぬに限る」
おじさんも頑張る!~山の話あれこれ~ 吉安輝修ちょっと縁起の悪い話題を…。山に縁遠い人にとってはどうでもよいことだが、山岳遭難死亡事故の原因をご存じだろうか?北アルプスや八ケ岳などを抱える山岳県でもある長野県警の統計では「転滑落」が一番で「発病」が二番に続く。山で発病というのは意外だが、どうやら持病の心臓疾患に気づかずに登山という高負荷運動での発作という。高齢登山者の増加に比例しているようだ。
三番目が「疲労・凍死傷」となっているが、これも年齢が上がるにつれてリスクが高くなる。持論だが、我々年寄りは暑さ寒さへの耐性や体温調節機能そして体力が若い時に比べて思っている以上に落ちていて、気づいたら、いや気づく前に体が動かなくなるのではないか。若い時なら少々の無理をして高度を下げるか、避難小屋に向かうなどして、危険な状況下から逃げだすことができるが、その無理がきかない。よって道具を買いそろえる前に体作りが先ではないかと信じている。
以前にも書いた気がするが、晩秋の槍ヶ岳を目指していた時、高度を上げるにつれて雨がミゾレになり、とうとう雪となって吹雪となった。とにかく立ち止まると危険だと、一気に稜線の小屋まで上がって安堵したことがある。その途中でガイドに連れられた中高年女性のパーティーを追い抜いたが、2時間近くも遅れて顔面蒼白状態で山小屋に転がり込んできた。開口一番「死ぬかと思った」と恐怖を語っていたのを思い出す。体力さえあれば、これほど長時間厳しい環境下にさらされることもなかっただろうとつくづくと思った。
白馬岳周辺での記憶に残る遭難といえば、2006年の10月にガイドと登山中の女性パーティーが、急な吹雪のため低体温で身動きがとれなくなり、白馬の山小屋まで数百㍍という所で4人が命を落とした。2012年のゴールデンウイークにも白馬岳から小一時間の場所で6人が突然の吹雪で遭難死したのも派手に報道された。場所は離れて、1988年10月の立山、2009年7月の北海道のトムラウシでの大量遭難も低体温によるものだ。これらの遭難事故の教訓として、十分な装備や体力はもちろんだが、天候判断も重要だと思い知らされる。
とはいえ、しょせんは人智の及ばぬ天地の諸現象だ。神様、仏様ならいざ知らず、山の天気などピンポイントで予測などできるわけがない。遭難しないためには山なんかに行かぬに限るのだが…。
前置きが長くなってしまったが、白馬岳の山頂から2時間ばかりの所に雪倉岳避難小屋がある。名前の通り緊急避難のための小屋で、風雨をさえぎってくれるだけの施設だが、いざという時の心強い存在となる。
大きな声では言えないが、当初の計画では2泊目をここに予定していた。あくまで避難用で本来なら積極利用など御法度だが、人の少ないこの時期なら勘弁して貰えるだろうという、自分本位の身勝手なものだったことを白状する。

紅葉の北アルプス天狗原=高度を上げるにつれて雨がミゾレになり、とうとう雪となって吹雪となった

雪倉岳避難小屋=当初の計画では2泊目をここに予定していた