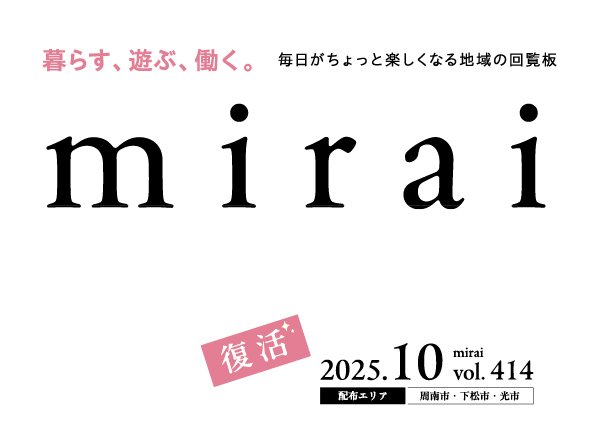コラム・エッセイ
針のむしろ
おじさんも頑張る!~山の話あれこれ~ 吉安輝修もう10年以上前の話になる。裏山に柚子の古木が十数本あるが、ほぼ放任状態で樹高は10メートルをゆうに超えていた。それが毎年良く実をつけているのだが、手が届かないので大部分は収穫できずに年を越しやがて落ちる。もったいないことだ。それも柚子の実が黄色く色付く時期になってようやくその存在に気付く程度で、鳥が種を運んで根付いたのだろうか雑多な木が競い合うように立っていた。しかもいつのまにか孟宗竹が侵入してきて竹林ならぬ竹藪と化しつつあり、足元には背丈にもなる笹がびっしりと生い茂りとても歩けるようなものではなかった。
子供の頃、そこには栗や柿、梅、ビワ、山椒などの果樹類が立っていて、その木立の間にはフキやミョウガ、ワラビなどが生えていた。時期になると祖母とかごを片手に採りにいっていたことを思い出す。
夕食前に三つ葉を摘んで来てくれと頼まれてツッカケ履きで採りにいっていたなあ…。まさに里山の風景だ。人と自然が上手く付き合いながら生活していた良き時代だったのかもしれない。今になって里山云々が見直されているが、当時はそれが普通の風景だったに違いない。
そうそう。春先になれば連日のようにワラビやタケノコ料理が続く。正直なところそれらをおいしいと思って食べていたわけではない。他に無いから食べるだけだ。この歳になってワラビとかタケノコの類はシーズン初めに何度かは食べるが毎食というのは勘弁だ。子供のころにもう一生分食べている。
話題があらぬ方向に向かいご先祖様の機嫌を損ないそうなのでもうやめよう。その代わりと言ったらますます罰当たりになるが、荒れるに任せていた裏山の整備は何年も前からコツコツと続けてきたのをあの世からきっと見ておられるに違いない。
今や田舎の現実は栗や柿などはもとより、田んぼの稲や畑の作物もサルやイノシシを肥やし、手を入れる気も失せていく。けれどもほとんど放置している柚子の木は何の被害をうけることなくたわわに実を成らしているではないか。柚子の実は酸っぱいし鋭く固いトゲは獣達を寄せ付けないのだろう。これだ!柚子なら荒れた里山再生のカギになるかもしれないと気付いた。以来、ヤブを刈り、ぼちぼちと柚子の苗木を植えてきてここ数年でようやく実をつけ始めた。
それと、雑草対策で牛を放牧するようになって久しいが、柚子の鋭いトゲは獣はもちろん牛も苦手なようで避けてくれる。柚子の苗木に影響は少なく牛との相性は良い。何より「のーくれ」には好都合だ。
先日、満身創痍で今年の柚子の収穫と出荷作業が終わった。厚手の腕抜きに溶接用の皮手袋。綿の厚手の上着に前掛けという重装備をしていてもトゲは容赦がない。夜には手袋を突き抜けて刺さったトゲを抜く。まるで針のむしろだ。

放任状態の柚子だが毎年よく実をつける

牛の放牧:苗木に影響は少なく牛との相性は良い

先日、満身創痍で今年の柚子の収穫作業が終わった