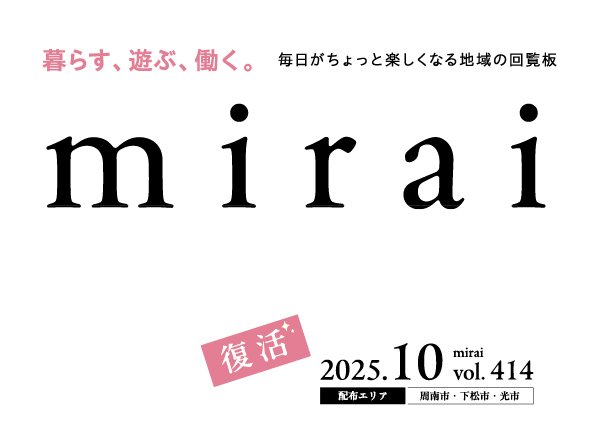コラム・エッセイ
「断腸の涙を流す②」
おじさんも頑張る!~山の話あれこれ~ 吉安輝修子どもの頃から何をするにしても切羽詰まって後が無い状況にならないと手が出ない。まだ時間があるさ。来週には手を付けよう。明日になったらやろうとズルズルと先延ばしにすることが常で、ギリギリになって焦りまくるというのがお決まりのパターンだ。
もう少し早く始めておけばよかったと後悔の繰り返しだ。この性格というか性分はとうとう何十年も改善されることなく人生の大半が過ぎて今に至る。
使わなくなって久しい我が家の古い家の解体作業も一例で、まずは家の中の残存物の片づけ作業が済まなければ始まらない。もう10年近くも前から来年はやる。今年こそやると言い続けていたが多忙を理由に手を出さない。
実のところ山暮らしというのは雑多な用事が山積し、やることが多いのも事実で優先順位がどんどん下がっていっても仕方がないが、夏は暑いし冬は寒いという「のーくれ気質」故の言い訳もあったことも白状する。
とはいえ、半ば危険家屋に分類される状態でこれ以上先延ばしもできない。解体業者が入る期日を決めてしまえば火が付くだろう。全身ホコリまみれになるのは覚悟の上だが、真夏に汗をかきながらは勘弁だ。それならと決行の時期を3月とし冬の間に片付ける算段だ。
自慢ではないが明治以前の築年数不明の超古民家で、大家族が暮らしていたこともありやたらと物が多い。二階の屋根裏部屋が物置になっていたが、歴代が使っていただろう多くのタンスや木箱、大量の布団、衣類が出てくる出てくる。物を粗末にしないことは良いことだが、叔父や叔母の子供の頃の物は新しい部類で祖父や曾祖父の小学校の教科書が出てきたのは驚いた。
祖父が日露戦争に兵隊で行ったのは聞いていたが、従軍章というのだろうか桐の箱に入ったバッジなども出てくる。それに100年以上も昔の新聞や書き物が出てくるとつい手が止まって見入ってしまうからいけない。
多少の資料的な価値はあるだろうと用意した箱に入れていたがこの調子で残せば倉庫を建てなければ追いつかない。じっくりと調査分類して展示すれば明治から現代までの生活史展が開けるかもしれない…と、思ったりもしたが、そんな余裕なんてない。
叔父叔母の名前が確認できるものはいとこ達に引き取ってもらい、残りの物は箱の数を決めて入るだけとし後は処分だ。大いに取捨選択に悩み、大量の財物を家の前で「ご自由どうぞ」の張り紙をして近所の人や通りがかりの人に持ち帰ってもらうなど、この数か月はご先祖様のご機嫌が気になって仕方のない日々だった。
周囲に足場が組まれ重機が搬入されてきた。それにしても機械の力で実にあっけなく取り壊されていく。当然寂しさや心残りもあり複雑な思いで眺めるが、負の遺産として次世代に押し付ける物が一つ減ったと思えば断腸の涙を流しながらホコリまみれになってのこの数か月の作業も報われる。

解体作業の前に家の中を片付けなくてはならない

「ご自由にどうぞ」の張り紙をして近所や通りがかりの人に持ち帰ってもらう

それにしても機械の力で実にあっけなく取り壊されていく:負の遺産として次世代に押し付ける物が一つ減った