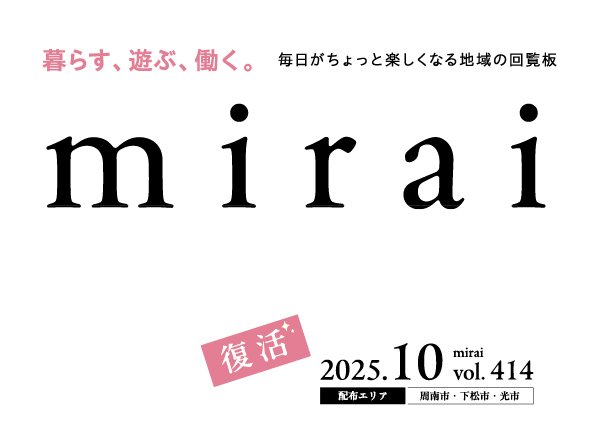コラム・エッセイ
第百三十五手 「2025年少年少女囲碁大会・全国大会」
「碁」for it 小野慎吾7月29・30日に東京の日本棋院で「第46回文部科学大臣杯少年少女囲碁大会・全国大会」が開かれました。対象選手は小学生の部、中学生の部の二つです。小学生の部は95人、中学生の部は96人が全国各地の県代表選手として出場しました。山口県からは小学生の部2人、中学生の部2人が出場しました。その内、1人が筆者の教室の生徒であったため、引率をしました。筆者が子どもの頃にはすでにあった大会で、筆者も毎年楽しみにこの大会に参加をしていました。筆者の頃は野球の甲子園と同じくトーナメント制でした。
1回戦は10時ごろに始まり、早ければ昼前には決着がつき、負ければ即帰宅するしかありません。筆者にとっては、はかない大会のイメージで、絶対に1回は勝って帰ろうと強く思った大会です。現在では6~8人前後の各リーグに分けられ、その中で3回戦を行うリーグ戦に変わりました。トーナメント制で1回負けて即帰宅は地方勢にとっては不憫だという事情を汲み取り変更になったと考えます。勝ち上がるにはリーグ戦でも1回も負けられないため、そういう意味ではトーナメント制と変わりはありません。
選手だけでも200人近くおり、小学生・中学生の参加となれば両親・引率者と一緒に来るのは必須です。そのため会場内には500人近い大会関係者がいました。気になる山口県選手は3人が0勝3敗、1人が2勝1敗という全体的はほろ苦い経験になったと思います。筆者は子どもの頃、小学生の部で6位・中学生の部で準優勝に入賞した事があります。小学生で入賞時は二段、中学生で準優勝時は六段くらいの棋力だったと記憶しています。現在は小学生でベスト8以上に入賞するには五段以上、中学生でベスト8以上は七段以上を有する必要がありそうです。
自身の子ども時代と比べて囲碁のレベルは数段上がったという印象です。昔は級位者も多かったのですが、現在はほぼほぼ有段者しかいません。全国大会の会場内で沢山の昔の知り合いと出会いました。筆者が40代で後輩、先輩にしてもその辺りの年齢で、知り合いの方が結婚をされて大会に出場できる年齢の息子さん・娘さんがおられる世代になったのだとひしひしと感じました。
熊本県在住の大学時代の他大学の先輩がたまたま応援に来られており、筆者の生徒と先輩の生徒で「交流対局」を数局させて頂きました。対局をした時には互いに全敗でどっちが全敗になるのかなと話しながら楽しく対局をしていました。
先輩が当コラムを見たことがあると言ってくれました。日刊新周南の電子版で当コラムは見る事が出来るのでそれで見てくれたのだと思います。一つの囲碁普及になっていると思い、今後も頑張って続けて行こうと思います。全国大会の全ての対局が終わり、帰省する時に当教室の生徒と先輩の生徒が「また次の大会で会おうね。」と言って別れました。その約束が叶わなくても囲碁を続けていれば、筆者が先輩と会ったように必ずまた会えると思います。
次の大会出場のために「碁」for it(頑張る)!

第46回少年少女囲碁大会・全国大会