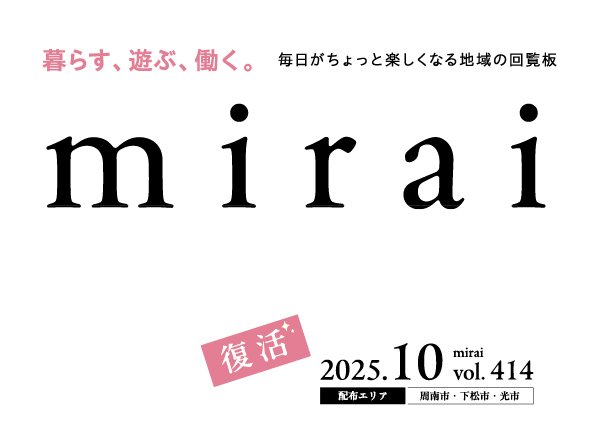コラム・エッセイ
- コラム・エッセイを探す
-
コラム名から探す
随想 季節の中で 西﨑博史(周南文化協会会長)
-
又 霜月(一)
秋が深まります。朝晩は冷え込むようになってストーブを出しました。7日は「立冬」。紅葉を楽しみながら山里では冬支度が始まります。 ともし火と砧の音のほか洩れず...
-
又 神無月(三)
神無月もあと二日。いよいよ霜月へ。先週は急に冷えました。23日は二十四節気の「霜降(そうこう)」。霜が降るとは上手い表現です。昔の人は早朝にうっすらと霜でおお...
-
又 神無月(二)
天高く馬肥ゆる秋。今では古風に聞こえる表現も、かつてはよく使っていました。「天高し」とは空気が澄んで空が高く感じられることです。「秋高し」や「空高し」も同じ意...
-
又 神無月(一)
葡萄から梨へ、梨から林檎へと果物も季節とともに移ります。過ぎゆく夏の終わりに葡萄を味わい、梨の登場に初秋を感じました。今年も須金の農園で収穫した「二十世紀」に...
-
又 長月(二)
秋刀魚が近年になく豊漁。店頭に並んで食欲をそそります。秋の味覚を早速いただきました。お酒も進みます。 和歌山県新宮市出身の詩人、佐藤春夫の「秋刀魚の歌」。〈...
-
又 長月(一)
初秋9月。日中は暑さがまだ厳しいですが、朝夕は幾分しのぎやすくなりました。7日は「白露」。草に降りた露が白く見える頃です。 夕焼 小焼の 赤とんぼ 負わ...
-
又 葉月(二)
お盆に墓参りしてご先祖に感謝を捧げながら家族や縁者が集って食事をともにします。互いの健康を祝い、ゆるやかな時が流れます。特別な月なのです。同窓会もほとんどがお...
-
又 葉月(一)
暦は8月。7日は「立秋」。うだるような暑さに閉口します。北海道も九州も変わらぬ暑さに首をかしげます。避暑地で有名な軽井沢も暑いです。日本列島に避暑地はあるので...
-
又 文月(三)
7月半ばを過ぎて蝉の声をようやく聴きました。「今年は蝉が鳴かないね」「猛暑で土の中から出てこられないのだろうか」などとよく話題になりました。真相はどうなのでし...
-
又 文月(二)
ソーダ水の中を貨物船がとおる 小さなアワも恋のように消えていった ユーミンこと松任谷由実の「海を見ていた午後」の一節。この季節になるとラジオから時折流れて...
-
又文月(一)
この随想も7月で4年目に入りました。令和4年7月7日に初めて随想を掲載して今回で76回を数えます。初回で「春夏秋冬。美しい四季は日本人の豊かな感性を生み出しま...
-
再々水無月(二)
九州北部とともに山口県は8日、梅雨入りしました。毎日のように雨が降ります。紫陽花(あじさい)が雨に映えます。咲き始めて時が経つにつれて色を変えることから「紫陽...
-
再々水無月(一)
山々が深い緑に包まれます。里ではゆすらうめ、梅が実ります。水辺ではふんわりと蛍が舞う季節です。早や6月。週末ごとに蛍まつりでにぎわいます。周南市では7日に和田...
-
再々皐月(二)
田植えの季節です。中国山地の山深い里では4月から5月の連休にかけて始まり、これから6月にかけて平地でも水を張った田に苗を植える姿が見かけられます。秋の収穫とと...
-
再々 皐月(一)
若葉から新緑へ。木々の葉が色を濃くします。季節とともに萌葱から緑、深い緑へと変わっていきます。いよいよ皐月。1日は八十八夜。5日の端午の節句は立夏と重なりまし...